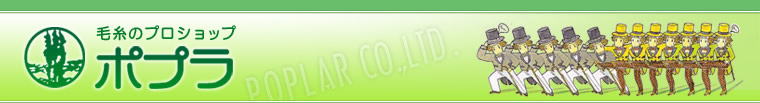
毛糸や編み針などの編物用品や編物グッズを利用することで、様々な編物を作ることができます。
これらの編物用品や手編み技法は、どのように生まれたのでしょうか。編物の歴史についてご紹介いたします。
糸や籐、ツルや竹などをねじり寄せて手編みする方法は、人類が必要に迫られて編み出した技術でした。
そのため石器時代から編物はあったと考えられています。また、漁業に必要な網も昔から作られていて、この技術も手編みの技法と関係しているといわれます。
最古の編物は3世紀頃のもので、シリアにある古代遺跡から発見されました。手編みされた小さな帽子や靴下から、織物用品はかぎ針を使ったと考えられています。そしてアラビア商人やムーア人たちによって、編物技術や編物用品が世界中に伝わりました。
北欧やイギリスで2本針の織物用品が使われるようになり、ドイツでは毛糸、麻糸、綿糸による手編みが始まりました。フランスやスペインでは、手編みの手袋や靴下が発展します。イギリスやドイツでも絹の編み靴下が流行し、各国で同業組合(ギルド)が発展しました。機械による工業化も進み、1595年にはイギリスのウィリアム・リーが編み機を発明しました。 やがて、クリミア戦争や第一次世界大戦などの大きな戦争が起きるようになり、編物の需要も拡大します。そのため女性たちの間で、家族や趣味のために編物をする風習が盛んになりました。
日本では1873年の明治時代に、東京にある女学校で編物教育が始まっています。1875年には千葉に官設牧場が開設され、羊の飼育も始まりました。改良されたメリヤス編み機も日本に輸入され、織物産業も発達します。第一次世界大戦で女性が社会進出を果たすと、カーディガンやニットが大流行します。そのため1955年にJIS規格が設けられ、網目記号などが統一されました。
当社は毛糸や織物用品専門の通販サイトです。手編みに欠かせない毛糸や編物グッズを、豊富に取り揃えています。クロバー毛糸や野呂英作の毛糸も数多く品揃えしています。毛糸一玉からでも購入が可能です。初心者やベテラン、プロとして活躍されている方も、ぜひご利用下さい。